関連公表物
-

日本と世界の課題2025ールールなき時代にどう向き合うか
NIRA総研
-

日本と世界の課題2024-新しいシステムを模索する
NIRA総研
-
日本と世界の課題2023-歴史の転換点に立ち、未来を問う
NIRA総研
-

日本と世界の課題-ウィズ・ポストコロナの地平を拓く-
NIRA総研
-

2050年の夢【テーマ別】
NIRA総研
-
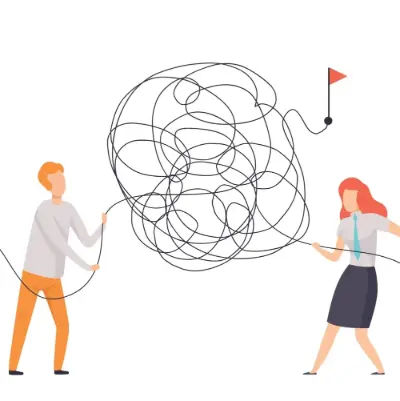
日本と世界の課題2025【テーマ別】
NIRA総研
-
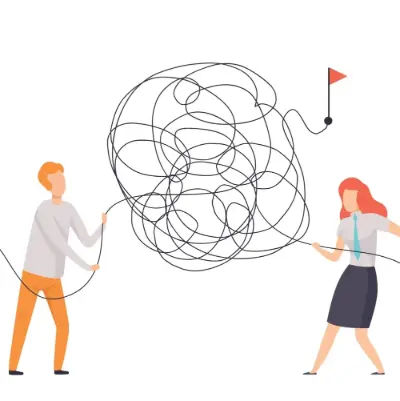
日本と世界の課題2025【氏名順】
NIRA総研
-
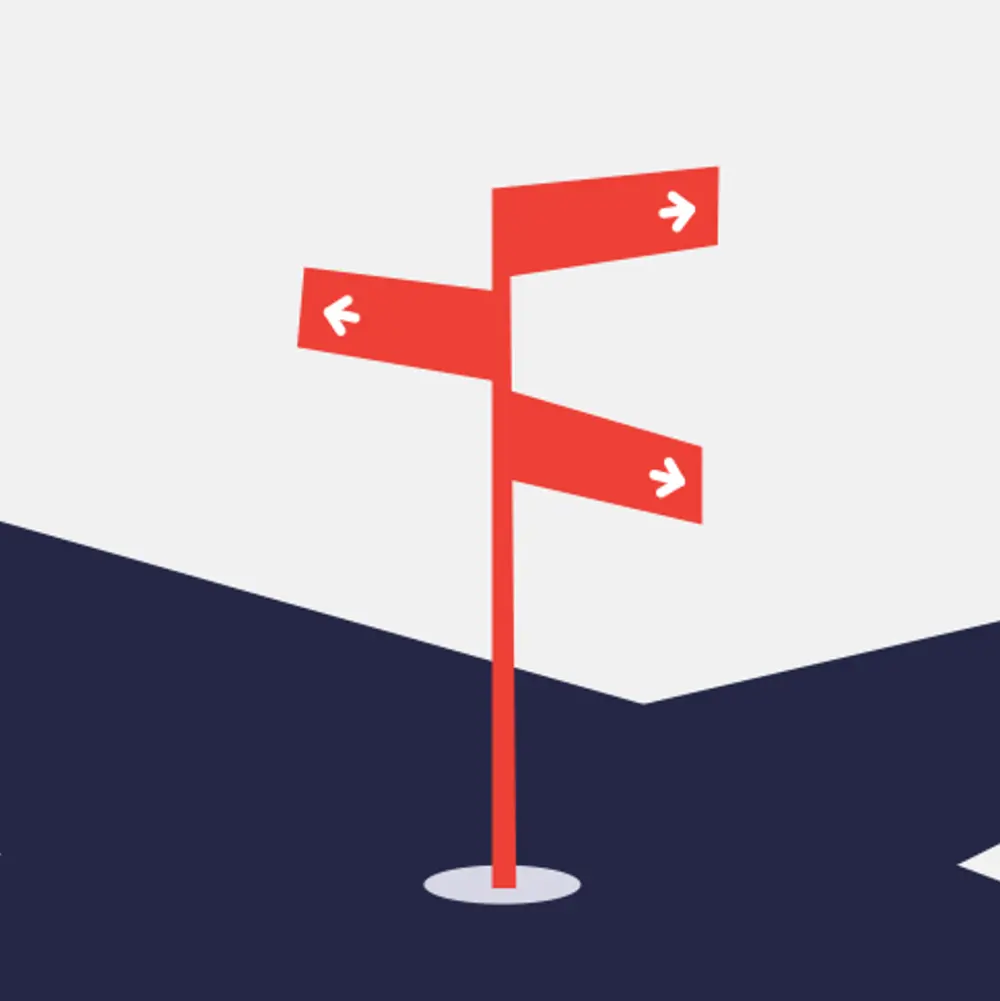
日本と世界の課題2024【テーマ別】
NIRA総研
-
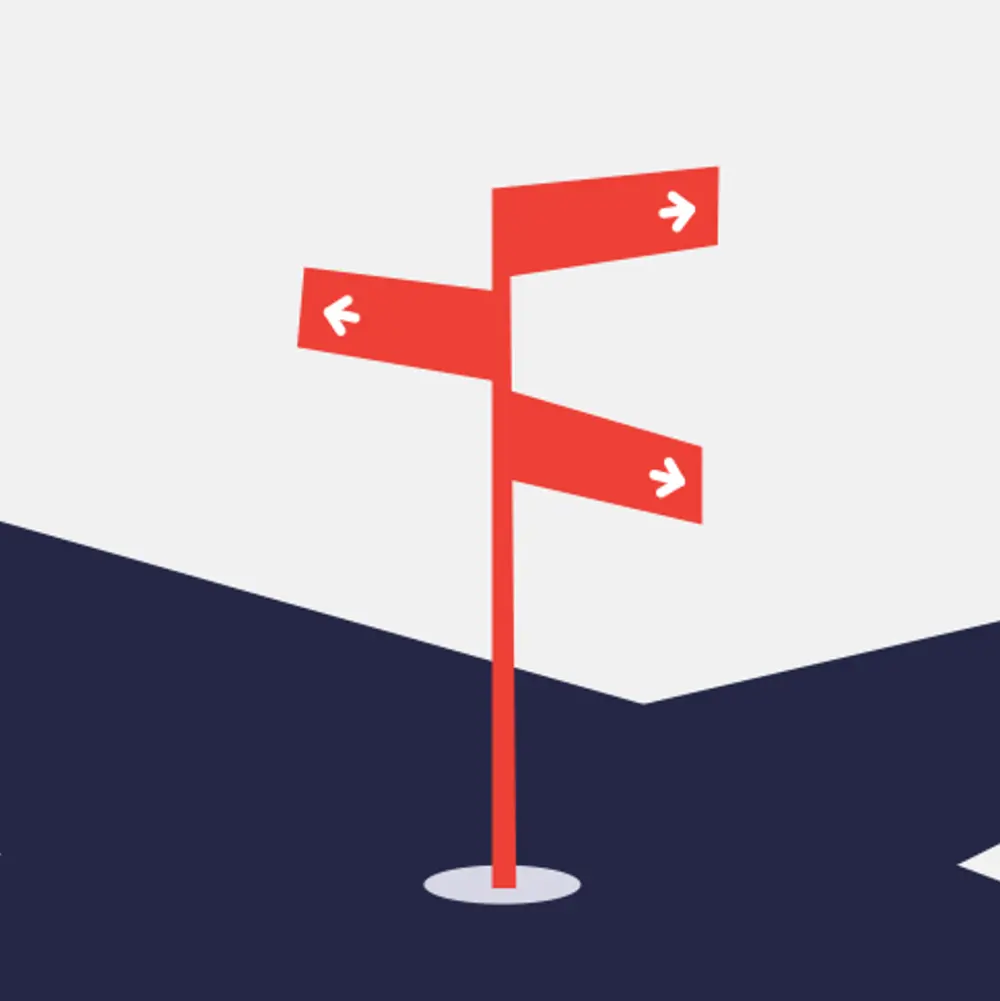
日本と世界の課題2024【氏名順】
NIRA総研
-

日本と世界の課題2023【テーマ別】
NIRA総研
-

日本と世界の課題2023【氏名順】
NIRA総研
-

日本と世界の課題2022【氏名順】
NIRA総研
-

日本と世界の課題2021
NIRA総研
